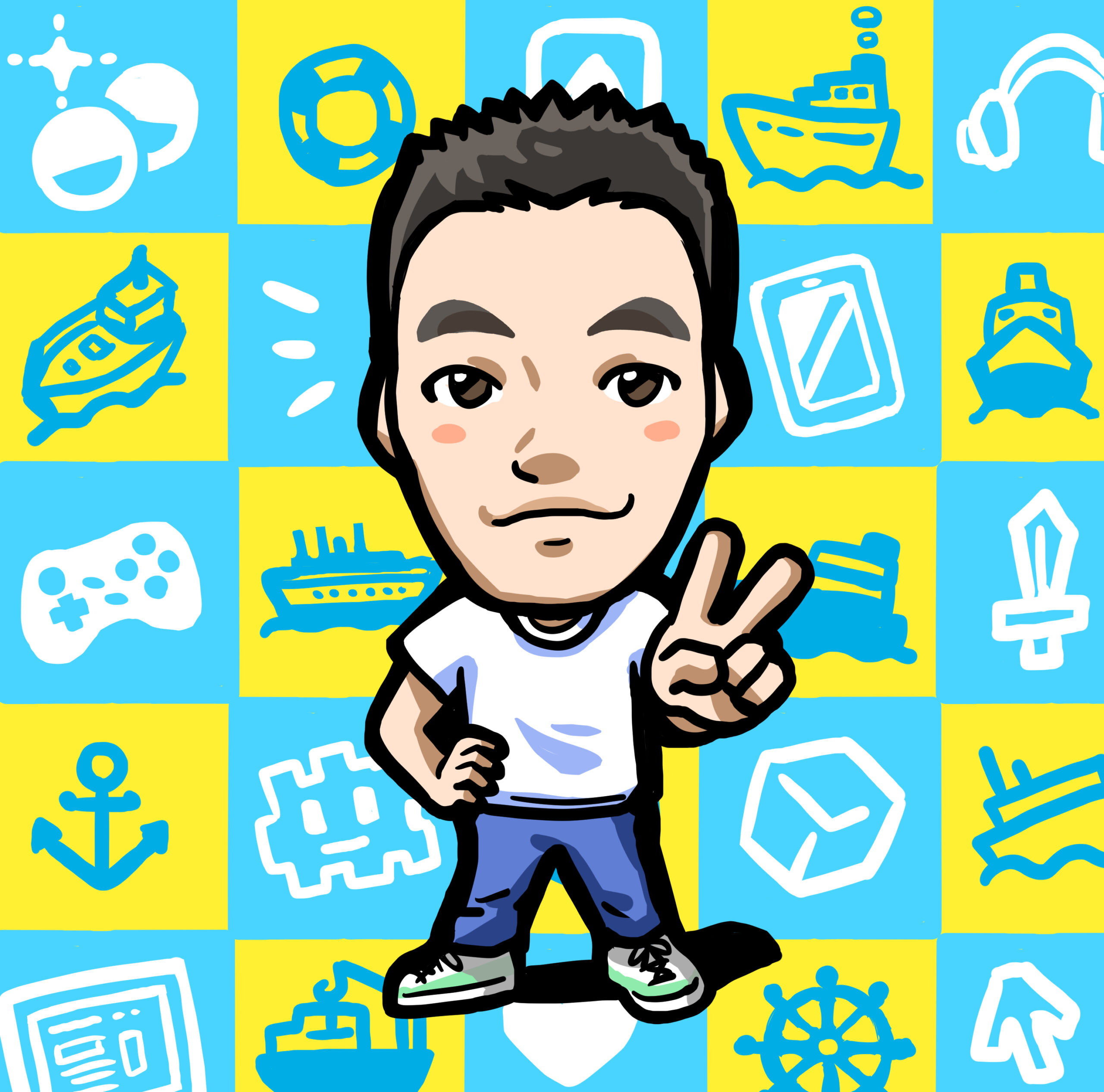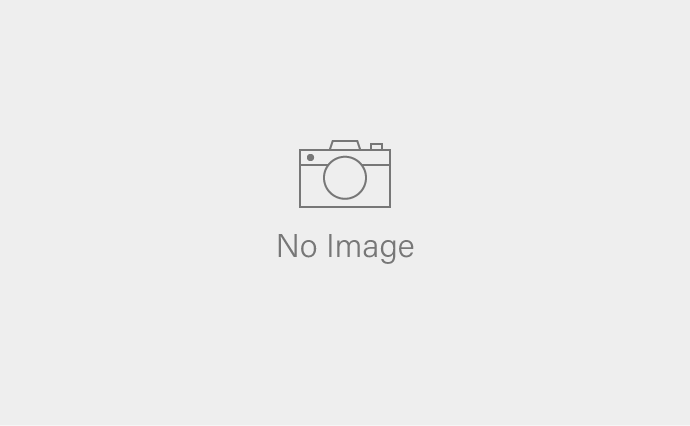みなさん、こんにちは。ヨーイングの総合ブログへようこそ!
今回の記事はメディアリテラシーについて、私のSNS・ブログの執筆経験を基にお話する内容です。
この記事はメディアの一員として、ブログやニュースなどの皆さんに参考・知っておいてほしい情報を随時更新しよりよい記事へと作り替えながらお伝えしていきます。
それでは、どうぞ!
まず初めに私のブログ・SNS歴について
私のブログ歴は、1年以上あります。SNS(LINE・旧ツイッター)歴はLINEの投稿歴が10年以上、ツイッターが半年以上です。特にLINEは身内向けにVOOM・プロフィールコメントを1週間に1回の頻度で更新できています。
そして、SNS・ブログをやっていくうちにメディアリテラシーとは何なのか本格的に考え始め当記事を書くことを決めました。
本題のメディアリテラシーとは?
メディアリテラシーの定義
メディアリテラシーとは、新聞やインターネット・テレビなどの情報を読み解くことを言います。
メディアリテラシーとは、様々な人が作り変えた情報を読み解くことだともいえるでしょう。
リテラシーの本質・大切なこと
リテラシーの本質は、趣味以外での生活場面においては「常に疑うこと」、趣味においては「間違いを見つけること」(趣味においても「常に疑うこと」が理想ですがそんなことしてたらつまらないでしょう)です。
「常に疑う」とは、主に何(対象となる人や物など)・なぜ(理由や原因)・どのように(プロセス)を臨機応変に考えることを言います。
常に疑い考えることはリテラシーの基本中の基本ですが、多くの人が現実逃避しがちなことだと思います。(みんなが情報を常に疑っていたのなら、偽情報や根拠がなさそうな噂は今より広まりにくいと思います)
常に疑うことは、マスコミやブロガーなどにとっての理想のあるべき姿といえるでしょう。
常に疑うことは恥ずかしくない。むしろ良いこと
常に疑った結果ひねくれたり、極度に偏ったり人によっては幼稚に見える考えに至ったとしても恥ずかしいことではありません。後で正せば良い話です。
なお、常に疑うことには専門知識は不要です。
メディアの情報の作り手は人間。だから情報が間違っていることがある
インターネット・テレビ・新聞などの情報は、当たり前ですが人が作ったものであり間違っていたり極端に偏っている(言葉巧みに情報が作られているので情報のプロでも分からない時もあるでしょう)ことがあります。
我々ブロガーの話になりますが、「間違いは後で正せば良い。とりあえず書いて記事のレベルを上げよう」という風潮があります。
これは、某有名ブロガーが人気記事で書いているほどのことです。
ただ、個人的には命や財産に関わる重要な情報は、間違えたらすぐに訂正・対応するのが全ブロガーの使命だと思っています。
アフィリエイト記事などを読むときの最低限のポイント
アフィリエイト記事などを読むときは、タイトルや序文よりも中身の文章を見ることが大切です。
なぜなら、タイトルや序文(リード文といいます)は書き手(ライター)が読んでほしいがために考えた文章であり記事の中身と釣り合わないときがあるからです。
情報の受け手も必見!作り手にとってのリテラシーで大切なこと
使う言葉によって意味や印象が異なってしまうフレーミング効果
心理学にフレーミング効果という使う言葉や表現によって意味や印象が異なってしまい、情報の受け取り方も違ってしまう現象があります。
これだけでも意識してブログ・SNSなどを書いていくと良いと思います。
この人には何かあるなと思ったら、確実に少しずつ裏取りをするのが理想
ブロガーなどの記事を見て「何か怪しいな」と特徴や文章などで感じることがあるときがあるでしょう。
そんなとき、その怪しさを裏付ける証拠を探していくのが裏取りとなります。
この裏取りによって信頼できる情報を抜き出し自分の貴重な情報源となり得ます。
最後に
私のSNSやブログ・現実での人生経験上の話として
上手く例えることができないため、説明が難しいですが普通に自分に優しく、人に厳しい人(逆も同じ)というのはなにかあったとしても、メディアリテラシー・メディアにおいても人生においてもさほど問題にはならないでしょう。
一方、極度もしくはかなり人に厳しかったりしてそのバランスが偏っている人は要注意だと思います。
まとめ
- メディアリテラシーとは「常に疑い考えること」
- メディアも人間。間違えることがある
- 言葉の受け取り方が変わるフレーミング効果には要注意!
どうだったでしょうか?
メディアリテラシーと聞くと、難しく身につかないスキルだと思いがちですが、そんなことないとこの記事で分かっていただけたら幸いです。
今後とも総合ブログ(雑記ブログ)として情報発信していきたいのでよろしくお願いいたします。
![[興味がある方必見!]100%全力ヨーイングのお役立ち総合ブログ](https://sougoublog123.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-IMG_3977-scaled-1.jpeg)